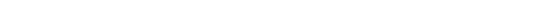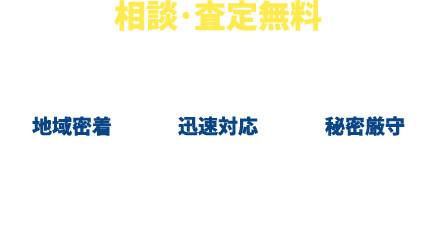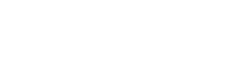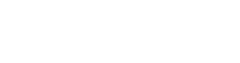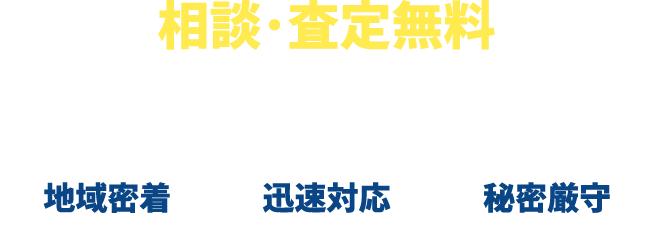
2025年4月13日
【コラム】トラブル急増!「デジタル遺産」とは?
「遺産」と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか?
みなさんイメージされるのは、「不動産」や「宝石」・「預貯金通帳」などをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
近年、ネット銀行やネット証券などのデジタル形式で資産を保有される方も増えており、相続の際にトラブルに発展する事例が増えています。
今回は今後さらに増えることが予想されている「デジタル遺産」についてご紹介します。

1.デジタル遺産とは
「デジタル遺産」とは一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことを指します。
またその中でも金銭に関する財産とそうでない財産に分けることができます。
金銭・資産に関する財産には、ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨(暗号資産)といった金融資産があります。
また、電子マネーの利用残高や各種ポイントやマイレージ、定期課金サービスなどの有料会員サービスも該当となります。

一方で、金銭に関しない財産は「デジタル遺品」と呼ばれます。
デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報などを指します。

今回は「デジタル遺産」に焦点を当て、相続時のトラブルへの対策法をご紹介します!
2.「デジタル遺産」の特徴
①本人しかわからない情報で管理されている
デジタル遺産は、スマートフォンやPC、クラウドデータ上で管理されているため、相続人がその存在に気づかないことも十分に考えられます。
また、存在を認識していたとしてもスマートフォンやPCにはロックを解除するためのパスワードは必要であることや、
管理上のログインIDやパスワードを入力しなければデジタル遺産の詳細は確認することはできません。
特にネット銀行やネット証券などの金融資産へのログインは複雑になっていることが多く、相続人が情報を取得することは難しいでしょう。
②定額利用(サブスクリプション)が解約されず課金されたままに…
故人が音楽・動画、オンラインサロンなどの有料会員サービスを定額利用(サブスクリプション)していた場合には
解約されないまま、課金が継続されてしまいます。
③相続手続きが複雑になりやすい
デジタル遺産の相続手続きの流れは、一般的な遺産と基本的に同様です。
しかし想定よりもデジタル遺産の数が多いケースも多く、また相続の為の名義変更などの対応が必要となります。
そのため情報を取得するにもかなりの労力と時間が必要となります。
やっとの思いでデジタル遺産の情報を取得した後も、相続財産に該当するのか、また相続財産の評価額を計算しなければいけません。
3.相続における「デジタル遺産」のトラブルとは
相続において複雑な「デジタル遺産」ですが、面倒だからと放置してしまう後々トラブルに発展する可能性もあります。
下記では想定されるトラブル事例をご紹介します。
①遺産分割協議をやり直さなければならない
相続の際には、相続人全員で遺産分割協議を行い、故人が残した財産をどのように分けるか話し合いをしなければなりません。
また、相続人全員が合意をしなければいけません。
やっとの思いで遺産分割協議がまとまった後に、デジタル遺産の存在が判明した場合にはそのデジタル遺産についての遺産分割協議をしなければならず、相続人にとっては大変な手間となります。
②重加算税が課される可能性も
また資産価値が高いデジタル遺産の放置は、相続税の追徴の恐れもあります。
デジタル遺産を相続遺産に含めなかった事実に、故意があったと判断された場合には
相続人には重加算税が課されることとなります。
③期限後申告や修正申告する必要がある
相続税の申告には、相続が発生した日から10カ月以内という申告期限が定められています。
そのため、相続税の申告期限を過ぎてからデジタル遺産の存在を知った場合には「期限後申告」を、
すでに相続申告をした後であれば「修正申告」をしなくてはなりません。
「期限後申告」・「修正申告」ともに、ペナルティ(附帯税)が生じます。
自ら期限後申告や修正申告をした場合には、追徴税額の税率は低く抑えられますが注意が必要です。
4.「デジタル遺産」を生前整理しておくことでトラブル回避
上記のようなトラブルを回避するためにも、デジタル遺産を生前整理しておくことが重要です。
①アカウントのIDやパスワードを整理
契約しているサービスは、アカウントのIDやパスワードをリスト化しておき、整理しておきましょう。
また整理の方法は、手書きでも構いませんし、エンディングノートを活用するなど様々な方法がありますのでご自身にあった方法で整理しましょう。
また、リスト化したものは、どこに保存しているのかご家族に伝えておくことで、いざというときにすぐに情報を共有することができます。
特にネット銀行やネット証券、定額利用サービス(サブスクリプション)のID・パスワードは必ず行うようにしましょう。
お金が関係することだけに、早めの対応や解約が必要となります。
②契約中のサービスの内容を見直す
現在契約中の定額利用サービス(サブスクリプション)について、それらが必要かどうか定期的に見直しをしてみてはいかがでしょうか。
サービスの加入数が多いほど、後々の契約手続きが煩雑となります。
利用頻度の少ないサービスは、生前整理の一環として解約しておくことをおすすめします。
③見られたくないデータは整理しロックをかける
相手が家族であっても見られたくないデータは誰しもあるものです。
またご自身が亡くなった後に家族が見てしまうことで、心に傷を負ってしまう恐れのあるデータなら
見れなくしておくこともお互いの為かもしれません。
そのような見られたくないデータは整理し、ロックをかけておきましょう。
また死後の扱いについても「削除してほしい」などの意思表示しておきましょう。
④エンディングノートや財産目録を作成しておく
エンディングノートや財産目録(財産の一覧表)を作成することで、財産の中身や処分の方法を家族に伝えることができます。
エンディングノートとは、自分自身に万が一のことがあったときに備えて、自分に関する様々な情報をまとめておくノートです。
エンディングノート内にデジタル遺産に関する項目をつくり、アカウントのIDやパスワードを
一緒に記載しておくとその後の相続時の手続きが円滑に進みます。
なお、エンディングノートに記載した内容には法的効果が生じません。
遺言書とは区別して使い分けるようにしましょう。
⑤死後事務委託契約を結んでおく
デジタル遺産の処理方法として、死後事務委任契約が使えます。
死後事務委任契約は、死後に発生する事務手続きを第三者に委託する契約で弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
死後事務委託契約で依頼できる手続きの一部
・行政への手続き(死亡届、健康保険や年金停止などの申請)
・銀行口座の解約
・不動産などの名義変更
・部屋などの清掃や家財の処分
・WEBサービスやデジタルデータの解約・処分
専門家にあらかかじめ死後事務契約を結ぶことで、死後発生する一切の事務手続きを任せておけば
相続人に負担をかけることなく相続手続きを進めることができます。
デジタル遺産の処理を含め、事務手続きを一任したい方には、死後事務委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。
費用については10万円~100万円が相場です。
5.まとめ
デジタル遺産は、財産の存在に気づかない可能性があることを認識しておく必要があります。
資産価値の高いデジタル遺産の存在が死後そのまま放置されると、遺産分割協議書のやり直しや追徴課税の発生などのトラブルにも発展します。
相続人に迷惑をかけない為にも、デジタル遺産の生前整理について一度考えてみてはいかがでしょうか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
滋賀県で空き家の売却を検討されている方は、リユースせいわへご相談ください。
空き家・土地の売却に関するご相談は無料で承っております♪
↓無料査定はこちらから
↓リユース事例はこちらから
===================================
リユースせいわフリーダイヤル📞0120-985-478
定休日:水曜日
〒520-3031 滋賀県栗東市綣6丁目10-15 道寄473番館 2階
TEL:077-532-0101
FAX:077-532-0105
===================================
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。