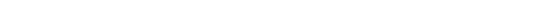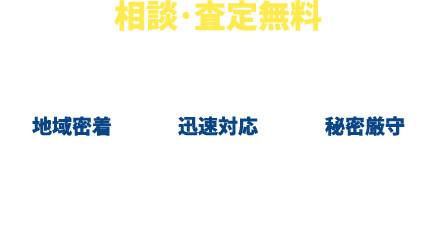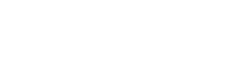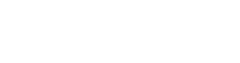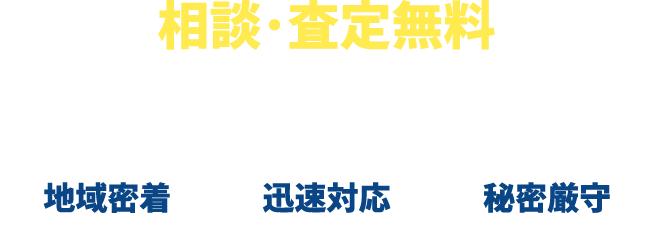
2025年6月13日
【コラム】いつかは起こる巨大地震…~空き家の地震対策してますか?~
「地震大国」とも呼ばれる日本では、世界で発生しているマグニチュード6以上の地震の約2割が日本周辺で発生しています。
また2025年1月、政府の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震が今後30年以内に起こる確率について、
これまでの「70%から80%」を「80%程度」に引き上げ公表しました。
調査委員会は、確率が10%上がったわけではないと説明したうえで、いつ地震が起きても不思議はない数字で
あることには変わりないと地震に対する備えを呼び掛けています。
2024年1月に発生した、「能登半島地震」では多くの空き家が倒壊し、避難経路の妨げや復興の遅れが問題視されています。
今回は、空き家が災害時にもたらすリスクについてご紹介します。

1.いつかは起こる巨大地震
先ほどもお伝えした通り、2025年1月に政府の地震調査委員会が南海トラフ巨大地震の発生確率を引き上げました。
地震調査委員会によると南海トラフでは約100~200年の間隔で大地震が発生しており、
昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから、切迫性の高い状態だとしています。
そもそも巨大地震とは、一般的にマグニチュード8以上の地震を指します。
2011年3月11日に発生した東日本大震災はマグニチュード9クラスの規模となり、
日本国内観測史上最大規模だと言われています。
東日本大震災から14年が経過しました。
改めて、近い未来に起こるかもしれない地震への備えについて確認していただきたいと思います。
2.空き家が災害時にもたらすリスクとは
適切に管理されずに放置された空き家は、家屋の構造の強度が徐々に弱まってきます。
そのため、地震が発生した際に倒壊するリスクが高くなり、近隣住民の安全や財産に多大な危険を
及ぼすかもしれません。
①倒壊の危険性
空き家はきちんと維持管理されていないことが多く、建物の老朽化が進んでおり耐久性が低くなっています。
このため、地震が発生すると壁や基礎部分に亀裂が発生し、倒壊する危険性が高くなります。
また、空き家の周囲のブロック塀やその他構造物がある場合、
それらが近隣の建物や住民に被害を及ぼす可能性も十分に考えられます。
②道路の封鎖により避難経路・緊急輸送時の妨げに
空き家の倒壊により、緊急輸送路や避難路をふさいでしまう恐れがあります。
災害発生時の避難や応急活動の妨げは過去の地震被害においても発生しており、問題視されています。
③空き家の所有者が不明の為、復興が進まない
2024年1月に発生した能登半島地震では、地震被害のあった空き家の処理も問題となっています。
2020年に珠州市が行った調査では、市内の住宅7,170戸のうち、空き家は1,490戸と約2割が空き家と報告されています。
能登半島地震では空き家が多い地域も多く復興作業の遅れに影響を及ぼしています。
損壊・倒壊した空き家を公費解体する場合は、原則所有者の同意が必要となります。
所有者不明の場合は、2023年4月施行の改正民法により裁判所が選任した管理人に処分を任せる財産管理制度を活用することで処分することができます。
しかしながら、上記のように解体に手間がかかる空き家より、所有者が分かる空き家から先に手をつけざるを得ないのが実情です。
3.空き家の活用・管理について見直してみませんか?
上記では空き家が及ぼす地震災害時のリスクについてご紹介しました。
地震が発生した際、すべての被害を防ぐことは難しいかもしれませんが、正しい管理・点検で防ぐことができることも多くあります。
下記では日頃からの管理・点検についてご紹介します。
~日頃から備える空き家の管理・点検方法~
①屋根や外壁
屋根や外壁に亀裂やずれ、ヒビ割れなどがあると地震の揺れで外壁が崩れたり、瓦が落ちてきて
隣家や通行人に被害を及ぼすかもしれません。
屋根や外壁の定期的な点検と補強を行うことで、被害を最小限に抑えることに繋がります。
②外構部分
外構部分の耐震は忘れられがちな点でもあります。
しかしながら、2018年に発生した大阪北部地震では小学校のプールのブロック塀が倒壊し、
登校中の女児が亡くなるという痛ましい事故が起こりました。
特に通学路や避難路などに面して設置されたブロック塀の安全確保はとても重要です。
ブロック塀などの構造物の責任は所有者にあります。
定期的な点検と、倒壊する恐れがあるものには転倒防止対策を講じましょう。
③窓
地震が発生すると、建物全体・窓枠に大きなゆがみが生じることでガラスがゆがみに耐えられずわれてしまいます。
割れた窓が近辺に散乱してしまうと、避難時にケガをするかもしれません。
窓の定期的な点検や飛散防止フィルムを貼っておくことで被害を抑えることができるでしょう。
上記は一部の対策例となりますが、空き家の定期的な管理・点検を行うことで被害を最小限に抑えることができるかもしれません。
しかしながら、遠方に所有する空き家がある場合には管理・点検を行えないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また管理には費用や時間も必要となり、金銭的にも精神的な負担となるでしょう。
今後、所有する空き家を活用する予定がない場合は下記の方法も視野に入れてみてはいかがでしょうか?
❶空き家の解体
空き家を放置せずに解体することで、地震発生時の倒壊のリスクを回避することができます。
老朽化した空き家を解体する際には、国や市区町村の補助金を受けることができる場合があります。
お近くの市区町村のホームページや窓口にお問合せすることをおすすめします。
❷空き家を改修
1981年(昭和56年)5月31日までの建てられた空き家は「旧耐震」の可能性があり、震度5強レベルの揺れでも建物が倒壊しない構造基準となります。
一方、1981年(昭和56年)6月1日以降の新耐震基準では震度6~7の揺れでも建物が倒壊しない構造基準となります。
築年数が古い空き家は「旧耐震基準」の可能性もあるため、
必要に応じて改修工事を検討してみましょう。
改修工事には補助金制度を利用することができるので、お近くの自治体に確認しておきましょう。
❸空き家を売却
空き家は放置することでどんどん老朽化が進み、被害のリスクが高まります。
今後、お住まいになられたりする予定がない場合は売却することでリスクを回避することができます。
空き家を売却するには専門家や不動産会社に相談することをおすすめします。
また、自治体が運用している空き家バンク等の制度もありますのでこちらも検討してみてはいかがでしょうか。
3.まとめ
南海トラフ巨大地震の発生確率が上がったと聞くと、不安に思われる方も多いでしょう。
しかしながら、南海トラフ地震は過去に繰り返し起きており、時間の経過とともに次の地震に近づいているのは
間違いありません。
確立に一喜一憂するのではなく、地震が発生した際に起こりうるリスクに備え対策することが需要です。
実家を相続したのはいいがそのまま放置していませんか??
日本全国で「放置空き家」が問題視されています。
今一度、ご自身ができる地震対策について考えてみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
滋賀県で空き家の売却を検討されている方は、リユースせいわへご相談ください。
空き家・土地の売却に関するご相談は無料で承っております♪
↓無料査定はこちらから
↓リユース事例はこちらから
リユースせいわ
===================================
リユースせいわ
フリーダイヤル📞0120-985-478
定休日:水曜日
〒520-3031 滋賀県栗東市綣6丁目10-15 道寄473番館 2階
TEL:077-532-0101
FAX:077-532-0105
===================================
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
参考:NHK「南海トラフ巨大地震 30年以内発生確率「80%程度」に引き上げ」
中日新聞「倒れた空き家は勝手に壊せない…道路ふさぐ木造家屋、所有者不明が復興の壁に」
国土技術政策総合研究所「R6能登半島地震の被災市町村に関する住宅関連データ」